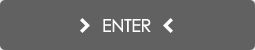企画展
ゆく河の流れ ―美術と旅と物語―

ヴェンツェル・ホラー《四季―四分の三半身の女性像》 1641年
| 開催期間 | 2012年10月27日(土)― 2012年12月24日(月・祝) |
|---|
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という一節にはじまる『方丈記』は、平安京を次々と襲った天災や社会の混乱を、鴨長明が冷静に見つめて描き出した文学の名作です。今なお多くの人々に愛され続けていますが、昨年の東日本大震災以来、時代を超えて、私たちにもよりいっそう深く響いてくるようになりました。
折しも今年は、『方丈記』が書かれて800年にあたります。これまで、歴史的にも『方丈記』に魅了された例は、数多く見出すことができます。文学では、明治時代に夏目漱石が『方丈記』を英訳したことや、堀田善衞が自身の戦争体験をもとに『方丈記私記』を執筆したことも、その好例といえましょう。大災害を経験した現在、新聞記事などで『方丈記』を参照したり、引用したりする例が増えました。再び、『方丈記』とそこに描かれた世界観が、急速に身近に感じられるようになった時代といえます。古くから天災に繰り返し襲われてきたこの国にあって、歴史に学ぼうとする姿勢が顕著になったともいえるでしょう。
本展は、『方丈記』を出発点として、文学と美術、時の流れ、芸術家の旅などをテーマに、約100点を展観するものです。まずは、柄澤齊の版画集『方丈記』を皮切りに、挿絵本などによって文学と美術の世界を紹介します。
『方丈記』のもう一つの特徴は、いわゆる五大災厄の記録が、鴨長明自身の前半生と重ね合せながら叙述されていることでしょう。変転する人生と変化していく社会の事象とが織りなされ、社会も人の生涯も「ゆく河の流れ」のように流転していきます。
そこで、「芸術家の旅」として、清水登之《ニューヨーク、夜のチャイナタウン》等の滞米期の絵画や、川島理一郎の滞欧期の《絵日記》、川上澄生《アラスカ物語》など、芸術家たちの創作に大きく影響することになった青年時代の旅に焦点を当てます。また石川寒巌の東京滞在と震災体験や、荒井寛方のタゴールとの交遊から生まれたスケッチ類なども紹介します。
これらのさまざまな芸術作品をとおして、私たちが生きる「現在」を見つめ直す機会となれば幸いです。
| 主 催: | 栃木県立美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会 |
|---|---|
| 特別協力: | 全国美術館会議(東日本大震災復興対策事業) |
| 協 賛: | ライオン、清水建設、大日本印刷、損保ジャパン、東武宇都宮百貨店 |
| 後 援: | 朝日新聞宇都宮総局、NHK宇都宮放送局、エフエム栃木、産経新聞社宇都宮支局、下野新聞社、とちぎテレビ、栃木放送、日本経済新聞社宇都宮支局、毎日新聞社宇都宮支局 |
平成24年度 文化庁 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
主な出品作品
- 序
柄澤齊《方丈記》1993-94年 - 文学と美術
オスカー・ココシュカ《テンペスト》(『シェイクスピアのヴィジョン』より)1918年、ウージェーヌ・ドラクロワ《シェイクスピア『ハムレット』》1864年刊 - 時の流れ
ヴェンツェル・ホラー《四季―四分の三半身の女性像》1641年、駒井哲郎《丘(日本の四季 春)》1975年 - 月をめぐる物語
J.J.グランヴィル《J.メリー『星々』》1849年、野村仁《'moon' score Jan.1,1980》1980年 - 歴史画のなかの平家物語
小堀鞆音《薩摩守平忠度桜下詠歌之図》1922年頃 - 芸術家の旅
川島理一郎《絵日記》1915年、川上澄生《アラスカ風景(白い墓標)》1924年頃、石川寒巌《大正大震災之一》1923年、清水登之《難民群》1941年、平澤熊一《台湾新竹風景》1935年 - 暗黒の時代
阿以田治修《うつろ》1943年、小杉放菴《金太郎遊行》1944年 - 穏やかな水辺で
カミーユ・コロー《ヴィル=ダヴレーの池》1847年、橋本邦助《水のほとり》1908年 ほか
※出品内容は、都合により変更になる場合があります。
 |
 |
| 柄澤齊 《方丈記》 1993-94年 |
板東敏雄 《風景》 制作年不詳 |
|---|---|
 |
 |
| 清水登之 《水辺のふたり》 1925年頃 |
刑部人 《水門》 1949年 |
 |
 |
| ジャン=バティスト=カミーユ・コロー 《ヴィル=ダヴレーの池(洗濯女たちと水飼場に来る馬)》 1847年 |
クロード・モネ 《サン=タドレスの海岸》 1864年 |