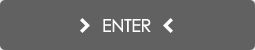企画展
特別展 浅川巧生誕120年記念
浅川伯教・巧兄弟の心と眼
―朝鮮時代の美
![企画展 [浅川伯教・巧兄弟の心と眼]](images/title.jpg)
《青花窓絵草花文面取壺》朝鮮時代・18世紀前半
大阪市立東洋陶磁美術館蔵(安宅昭弥氏寄贈) 浅川巧旧蔵
| 開催期間 | 2012年1月14日(土)― 2012年3月20日(火・祝) |
|---|
山梨県に生まれた浅川伯教(のりたか)(1884-1964)と巧(たくみ)(1891-1931)の兄弟は、大正初期に朝鮮半島に渡りました。彼らは朝鮮家屋に居をかまえ、現地の人々に溶けこみながら暮らします。やがて伯教は朝鮮陶磁研究の第一人者となり、また弟の巧も朝鮮の陶磁器および木工品について名著を残しました。彼らの活動で特筆されるべき点は、高麗青磁に比べ低く見られていた “李朝”-朝鮮時代(1392-1910)の陶磁器に世界に先駆けて注目し、その美を日本に紹介したことです。
1920年代以降、浅川兄弟の活動によって李朝の陶磁器や工芸品は一躍注目を浴びることになります。ふたりは時代を代表する陶芸家、研究者そして数寄者たちが朝鮮時代の美術を理解するためのよき協力者、導き手となりました。なかでも、彼らが柳宗悦(1889-1961)に影響を与え、そこに河井寛次郎(1890-1966)、濱田庄司(1894-1978)、富本憲吉(1886-1963)たちが加わったことによって、「民藝」運動は具体化していきます。
残念なことに巧は若くして世を去り、戦後、朝鮮から帰国した伯教も時代の変転のなかで調査や研究の成果を充分にまとめることなく歿しました。
本展は、浅川兄弟と柳宗悦が選び抜いた旧朝鮮民族美術館のコレクションをはじめ、伯教作の絵画資料や陶芸作品、柳自筆の原稿、そして同時代の陶芸家たちの作品など約200点を通して、今日改めて評価の気運が高まる浅川兄弟の事跡を、はじめて体系的に紹介するものです。
| 主 催: | 栃木県立美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会 |
|---|---|
| 特別協力: | 大阪市立東洋陶磁美術館、北杜市 |
| 協 賛: | ライオン、清水建設、大日本印刷、損保ジャパン、日本テレビ放送網、東武宇都宮百貨店 |
| 後 援: | 朝日新聞宇都宮総局、NHK宇都宮放送局、エフエム栃木、下野新聞社、とちぎテレビ、栃木放送、日本経済新聞社宇都宮支局、毎日新聞社宇都宮支局 |
| 企画協力: | E.M.I.ネットワーク |
章構成
第1章 浅川伯教・巧兄弟の心と眼
- 京城の暮らしの中で
- 浅川伯教の足跡
- 浅川巧の足跡
第2章 朝鮮民族美術館の設立―"民藝"の原点
第3章 浅川兄弟が愛した朝鮮陶磁の美
第4章 古典復興のうねりの中で
~富本憲吉・河井寛次郎・濱田庄司・石黒宗麿・川喜田半泥子・北大路魯山人~
※本展は巡回展のため、開催館により出品作が異なります。
※栃木会場では、《青花辰砂蓮花文壺》(大阪市立東洋陶磁美術館蔵)は所蔵館の都合により展示されません。ご了承ください。
 |
 |
| 《粉青刷毛目碗 鶏龍山茶碗 銘「東鶴寺」》 朝鮮時代・15世紀後半-16世紀前半 大阪市立東洋陶磁美術館蔵(鈴木正男氏寄贈) |
《粉青粉引碗 粉引茶碗 銘「渼芹洞」(ミクンドン)》 朝鮮時代・16世紀後半 大阪市立東洋陶磁美術館蔵(鈴木正男氏寄贈) |
|---|---|
 |
 |
| 《鉄砂草花文壺》 朝鮮時代・17世紀後半 個人蔵 |
《青花花鳥文壺》 朝鮮時代・18世紀 大阪市立東洋陶磁美術館蔵(鈴木正男氏寄贈) |
 |
 |
| 《白磁壺》 朝鮮時代・17世紀後半-18世紀前半 大阪市立東洋陶磁美術館蔵(鈴木正男氏寄贈) |
《辰砂蓮花文面取瓶》 朝鮮時代・18世紀 大和文華館蔵 |
 |
 |
| 《紙縒八角漆塗盤》 朝鮮時代・19世紀 日本民藝館蔵 |
浅川伯教《黒釉茄子茶入 銘「千草」》 個人蔵 |
 |
 |
| 河井寛次郎《白地草花絵扁壺》 1939年 京都国立近代美術館蔵 |
川喜田半泥子《井戸茶碗》 1940年頃 個人蔵 |